
第96号/1997.9
■災害時地下避難施設分科会発足
■複合型地下防災システム分科会発足
■深部地盤蓄熱システム分科会発足
■新燃料地下貯蔵システム分科会発足
■地下利用推進第1部会活動方針紹介
■地下センター調査研究組織図
■会員の皆様へのお知らせ
■災害時の地下避難施設に関する調査研究分科会発足■
本年度の社会開発システム策定事業の一つとして標記テーマ(昨年度より継続)の第1回分科会が7月15日(火)に開催されましたので、その概要を以下に紹介します。
1.背景・目的
阪神・淡路大震災では、地上構造物に比べ地下街や地下駐車場の被害が少なかったにもかかわらず避難場や救護所として利用されることはなかった。このことは、地下構造物の安全性がある程度認識されているものの、地下避難への恐怖、酸欠やガス漏れ、火災などへの不安があり、また、避難場や救護所としての諸機能が整備されていなかったためと思われる。一方、都市部に新たな単独防災拠点を整備することは、用地買収等の困難が予想される。そこで、都市部に位置し、耐震性のある公共施設として地下駐車場に注目し、防災機能を併設することにより、避難弱者である高齢者や病弱者が被災地区にとどまって難を逃れられる地下避難施設の構築を図る。
2.調査研究内容
昨年度の調査研究により得られた概念を基に、本年度は、自治体へのアンケート調査を実施し、本施設の導入を働きかけるとともに1~2の候補地を選定し、ケーススタディを行う。ケーススタディでは、候補地における技術的、制度的な条件を抽出・検討し、施設の概念設計および工事費等の算出を行うことにより災害時の地下避難施設としての実現性を検討する。
3.実施体制(敬称略)
| 分科会長 |
室崎 益輝 |
神戸大学 教授 工学部 建設工学科 |
| 分科会委員 |
熊谷 良雄 |
筑波大学 教授 社会工学系 |
| 〃 |
宮川 彰彦 |
(財)エンジニアリング振興協会 地下開発利用研究センター 研究理事 |
| 〃 |
仁木 将雄 |
石川島播磨重工業㈱ パーキングシステム事業部 技術部 部長 |
| 〃 |
笠原 勲 |
大成建設㈱ 技術研究所 環境研究部 部長 |
| 〃 |
廣田 昌憲 |
東京電力㈱ 建設部 建築課長 |
| 〃 |
五十嵐義則 |
能美防災㈱ エンジニアリング営業本部 部長 |
| オブザーバー |
小澤 典明 |
通商産業省 機械情報産業局 産業機械課 課長補佐 |
| 〃 |
竹内 茂 |
通商産業省 環境立地局 産業施設課 課長補佐 |
| 〃 |
萩谷 恵嗣 |
(財)駐車場整備推進機構 企画調整部 調整課長 |
| 事 務 局 |
深江 邦彦 |
(財)エンジニアリング振興協会 地下開発利用研究センター 主任研究員 |
| 幹 事 |
塩入 貢 |
大成建設㈱ 土木プロジェクト推進部 第二推進室 課長 |

■給水・給電等システムを考慮した複合型地下防災システム構想に関する調査研究分科会発足■
本年度の社会開発システム策定事業の一つとして、学識経験者と関係官庁の協力を得て標記分科会が発足しましたので概要を以下に紹介します。なお、本調査研究は平成8年度からの継続事業で今年が2年目となります。
1.背景・目的
1995年の兵庫県南部地震では、多くの人的・物的被害をもたらし、とりわけ防災拠点の混乱およびライフラインの寸断によって都市機能の脆弱性が露呈した。
そこで、本調査研究では地震の際にも比較的安全であった地下の利用のあり方を考えるとともに、現状の都市の持つ脆弱性を緩和するため、地下防災構想の一貫として無休型の給水・給電等支援システムを考慮した都市地域の複合型地下防災ネットワークシステムを構築することを目的とする。
2.調査研究内容
昨年度の調査研究は、兵庫県南部地震の被害と復旧、海外の防災対策システム等の文献調査、自治体へのアンケート調査等を実施した。さらに、防災施設、給水・給電施設と防災情報システムの基本方針と、それらを複合させた地下防災システムの構想について概念設計を行った。
本年度は、具体的な地域特性を加味するため、はじめに沿岸・平野モデルと山地・盆地モデルとなる都市を数箇所選定する。そして、モデル都市ごとの社会環境・自然環境条件、地域防災計画および地下空間利用を調査し、現況を把握する。昨年度の概念設計にこれらの結果を考慮して、複合型地下防災システムについて検討するとともに、事業化の可能性についての事例研究を行う。
3.実施体制(敬称略)
| 分科会長 |
小島 圭二 |
東京大学 教授 工学系研究科 地球システム工学専攻 |
| 分科会委員 |
河田 惠昭 |
京都大学 教授 京都大学防災研究所 巨大災害研究センター長 |
| 〃 |
鈴木 和男 |
自治省 消防庁 予防課 設備専門官 課長補佐 |
| 〃 |
伊藤 章雄 |
東京都 総務局 災害対策部 部長 |
| 〃 |
鳥居 盛男 |
横浜市 総務局 災害対策室 室長 |
| 〃 |
池田 恒彦 |
世田谷区 環境部 防災課 課長 |
| 〃 |
宮川 彰彦 |
(財)エンジニアリング振興協会 地下開発利用研究センター 研究理事 |
| 〃 |
宮川 保之 |
㈱大林組 技術研究所 空間アメニティ研究室 室長 |
| 〃 |
藤原 吉美 |
関西電力㈱ 土木建築室 土木課長 |
| 〃 |
石川 浩次 |
中央開発㈱ 技術本部 本部長 |
| 〃 |
宮島 圭司 |
中央開発㈱ 技術本部 技師長 |
| 〃 |
村田 昇 |
中央開発㈱ 設計本部 副本部長 |
| 〃 |
池座 秀夫 |
千代田化工建設㈱ エネルギー環境プロジェクト本部 参事 |
| 〃 |
片平 冬樹 |
東京電力㈱ 電力技術研究所 耐震グループ |
| 〃 |
野田 浩次 |
西松建設㈱ 土木設計部 副部長 |
| 〃 |
五十嵐義則 |
能美防災㈱ エンジニアリング営業本部 参事 |
| 〃 |
羽子岡 蕃 |
三菱電機㈱ 公共システム技術部 部長 |
| オブザーバー |
小澤 典明 |
通商産業省 機械情報産業局 産業機械課 課長補佐 |
| 〃 |
竹内 茂 |
通商産業局 環境立地局 産業施設課 課長補佐 |
| 事 務 局 |
田中 茂樹 |
(財)エンジニアリング振興協会 地下開発利用研究センター 主任研究員 |
| 〃 |
中村 裕昭 |
中央開発㈱ 技術本部 地盤環境・防災グループ長 |
| 〃 |
浜 康之 |
中央開発㈱ 東京支社 土木設計部 土質設計室 次長 |
| 〃 |
高橋 裕和 |
中央開発㈱ 技術本部 エンジニアリング地質部 副長 |

■深部地盤直接蓄熱システムに関する調査研究分科会発足■
本年度の社会開発システム策定事業の一つとして、標記分科会が7月29日(火)に発足しましたので、概要を以下に紹介します。
1.背景・目的
二酸化炭素による地球の温暖化や冷房排熱等による都市規模のヒートアイランドに関する問題が顕在化し深刻になっている。21世紀に向けて、国際協力、官庁、自治体など様々なレベルで温暖化対策や二酸化炭素排出削減の必要性と目標の数値化がさけばれており、抜本的な抑制策の開発が急務とされている。
そこで、都市部の大型ビルの下部にある軟弱地盤を対象に、垂直ボアホールを掘削し、夏に蓄熱、冬に熱回収して熱を暖房・給湯の主熱源として用いるシステムを提案する。本システムにより、夏季の太陽エネルギーや冷房排熱といった未利用エネルギーを効果的に恒温性の土壌に蓄え、冬季に必要な温熱源として利用することにより、都市部の二酸化炭素排出を大幅に削減することを目的とする。
2.調査研究内容
研究対象となるシステムは、夏季に太陽エネルギーや冷房排熱などの温熱をボアホールに蓄え、冬にボアホールから回収した熱を高層ビルの空調システムに利用するものである。ボアホールは、1mピッチで25本を1ユニットとし、直径10㎝程度かつ深さ数十~100mまで掘削することを想定する。また、ソーラーコレクタやゴミ焼却場排熱等の未利用熱源の併用を図り、暖房・給湯の熱源として用いる手法や地域冷暖房システムと組み合わせた構想も検討する。調査すべき研究内容は以下のとおりである。
(1) 低コスト型ボアホール建設法の開発
(2) 地下水流の影響抑制手法の開発
(3) 地中の熱流体移動予測計算法の開発
(4) システム・シミュレーションの実施
(5) 蓄熱利用システムの開発
3.実施体制(敬称略)
| 分科会長 |
落藤 澄 |
北海道大学 教授 大学院工学研究科 都市環境工学専攻 |
| 副分科会長 |
磯村 栄治 |
三菱地所㈱ 建築業務部 副長 |
| 分科会委員 |
宮川 彰彦 |
(財)エンジニアリング振興協会 地下開発利用研究センター 研究理事 |
| 〃 |
酒井 寛二 |
㈱大林組 技術研究所 副所長 |
| 〃 |
中田 礼嘉 |
㈱大林組 エンジニアリング本部 環境プロジェクト部 副部長 |
| 〃 |
井出 光夫 |
高砂熱学工業㈱ 技術開発部 部長 |
| 〃 |
片倉 百樹 |
東京電力㈱ 営業部 蓄熱推進部長 |
| 〃 |
松木 一郎 |
東北電力㈱ 営業部 お客様サービス 担当部長 |
| 〃 |
香山 康晴 |
前田建設工業㈱ 技術研究所 次長(研究第1グループ) |
| 〃 |
黒崎 幸夫 |
三井建設㈱ 技術研究所 第二研究開発部門 主席研究員 |
| 〃 |
陶 昇 |
三菱化学エンジニアリング㈱ 蓄熱事業部 部長 |
| 〃 |
横山 五郎 |
三菱重工業㈱ 冷熱事業本部 冷熱直販部長 |
| オブザーバー |
笠原 彰 |
通商産業省 資源エネルギー庁 公益事業部 熱供給産業室 課長補佐 |
| 〃 |
山田 知穂 |
通商産業省 資源エネルギー庁 公益事業部 開発課 課長補佐 |
| 〃 |
小澤 典明 |
通商産業省 機械情報産業局 産業機械課 課長補佐 |
| 〃 |
竹内 茂 |
通商産業省 環境立地局 産業施設課 課長補佐 |
| 事 務 局 |
早川 雅彦 |
(財)エンジニアリング振興協会 地下開発利用研究センター 主任研究員 |
| 〃 |
漆崎 昇 |
㈱大林組 環境マネジメント室 企画課 課長代理 |

■新燃料(超重質油)の地下貯蔵システムの可能性に関する調査研究分科会発足■
本年度の社会開発システム策定事業の一つとして、標記分科会が8月25日(月)に発足しました。本分科会の概要を以下に紹介します。
1.背景・目的
近年、電力各社では燃料の多様化に積極的に取り組んでおり、その一環として超重質油をエマルジョン化した新しい液体燃料が注目を浴びている。この新燃料の一部には、我が国において危険物の取扱いを受けないものもあり、このような新燃料の貯蔵においては、既存の石油タンク等のような規制を受けない利点がある。また、このような新燃料のコストが安価なことや非危険物であることなどの特徴を活かして、電力事業での火力発電所用燃料として検討対象になるなど、近年その消費量は着実な増加傾向にあると考えられる。
本調査研究では、既存の地上タンクに比較して、簡易な貯蔵システムを提案する。特に、周辺環境への影響を考慮し、地下空間を有効に利用するとともに、さらには今回対象とする新しい液体燃料の特徴を活かした貯蔵システムを構築することを目的としている。
2.調査研究内容
(1) 全体システムの構築
危険物保管用の鋼製タンクの基本性能の調査
超重質油の種類及び基本特性の調査
超重質油、重油、石炭の生産・消費動向等調査
焼却灰の再利用に関する調査、検討
全体システムの構築
(2) 貯槽方法の検討
貯槽方式の検討
貯槽構造・材料の検討
(3) プラントシステムの検討
既存プラントの貯槽形態の調査
新貯槽プラントに必要な配管、諸設備の検討
安全管理の調査
(4) 施工方法の検討
建設方法及びその実現性に関する調査
貯槽及びプラントの経済性に関する検討
3.実施体制(敬称略)
| 分科会長 |
國生 剛治 |
中央大学 教授 理工学部 土木工学科 |
| 分科会委員 |
西 好一 |
(財)電力中央研究所 我孫子研究所 地盤耐震部 部長 |
| 〃 |
小倉 秀 |
海上災害防止センター 調査研究室 室長 |
| 〃 |
宮川 彰彦 |
(財)エンジニアリング振興協会 地下開発利用研究センター 研究理事 |
| 〃 |
山本 博義 |
㈱荏原製作所 機械事業本部 開発統括室水力機械開発室 室長 |
| 〃 |
長谷川啓司 |
㈱荏原総合研究所 取締役 企画センター長 |
| 〃 |
島本 恭次 |
関西電力㈱ 原子力・火力本部 原子力・火力企画グループ 課長 |
| 〃 |
石崎 秀武 |
清水建設㈱ 技術開発センター 技術開発部 部長 |
| 〃 |
傳田 篤 |
清水建設㈱ 技術開発センター 技術開発部 副部長 |
| 〃 |
吉村 隆 |
清水建設㈱ エンジニアリング本部 建設エンジニアリング部 |
| 〃 |
小舩 利予 |
西武建設㈱ 技術部 部長 |
| オブザーバー |
遠藤 安昭 |
自治省 消防庁 危険物規制課 課長補佐 |
| 〃 |
福島伸一郎 |
通商産業省 資源エネルギー庁 公益事業部 電力技術課 電力技術班長 |
| 〃 |
小澤 典明 |
通商産業省 機械情報産業局 産業機械課 課長補佐 |
| 〃 |
竹内 茂 |
通商産業省 環境立地局 産業施設課 課長補佐 |
| 事 務 局 |
山路 俊文 |
(財)エンジニアリング振興協会 地下開発利用研究センター 主任研究員 |
| 〃 |
藤城 春雄 |
清水建設㈱ 技術開発センター 管理部 |

■地下利用推進 新分野開発専門部会(第1部会)活動方針紹介■
新分野開発専門部会(通称・第1部会)は、地下利用推進部会の一つとして夢のあるプロジェクトの研究活動を骨子に、首都機能移転モデルの地下利用基本構想の構築・利用計画等の検討や、大深度地下空間利用の可能性,課題,提案の取りまとめ等、全く新しい地下利用の形態・ニーズを探索することを狙いとして、平成8年度より活動が始まりました。
当部会は、種々の専門分野の委員で構成されているため、各委員より研究対象テーマの提案募集を行い「防災・環境空間」,「生活関連空間」,「物流空間」および「極限・未利用空間」の4つのグループに分けて調査研究を行っています。昨年度は、利用対象空間としての地下空間開発上の問題点の明確化や利用技術上の課題抽出,地下の特性を活かし且つ社会ニーズに対応した利用方法の提示,ならびに調査対象の絞り込みを行いました。
本年度は、昨年度の調査研究の成果を踏まえ、グループ毎に具体的な構想提案や実現のための課題提言を行う予定です。
以下に、それぞれのグループの活動方針を紹介します。
(1) WG-A:防災・環境
「都市火災のための地下歩道避難ネットワーク構想」について対象自治体に提案可能な内容としてまとめる。具体的には、地震時の避難危険度の高い地域をモデルケースとして構想をまとめ、投資効率の向上方策、補助金制度の活用も併せて研究する。
(2) WG-B:生活関連
モデル都市を想定して、地表に無くても良い施設を適切な場所の地下に移転させた場合、その跡地および移転先の地下ならびにその周辺一帯の地下を含めて、どの様な理想的な住環境が考えられるかを構想する。また、長期の地下滞在、居住に関し、深層心理面からの調査も併せて実施する。
(3) WG-C:輸送(物流)
「ながれ研究集団」の構想をベースとした地中飛行機構想を再調査し、2030年をターゲットにした地中飛行機輸送のニーズ、波及効果を検討する。さらに、その輸送空間の多目的利用に関しても調査を行う。
(4) WG-G:極限・未利用
「全く新しい地下利用の形態,ニーズの探索」をメインテーマとして、具体的には砂漠および海洋下(沿岸部)での新しい利用形態をケーススタディを通して提案する。
新分野開発専門部会(第1部会)名簿
| 部会長 |
森 清就 |
㈱熊谷組 |
| 副部会長 |
山口 隆志 |
新日本製鐵㈱ |
| 委 員 |
池尻 健 |
㈱青木建設 |
| 〃 |
小倉 貞夫 |
NKK |
| 〃 |
金井 恵嗣 |
㈱大林組 |
| 〃 |
寺井 徳雄 |
㈱奥村組 |
| 〃 |
中尾 健児 |
川崎地質㈱ |
| 〃 |
宮下国一郎 |
清水建設㈱ |
| 〃 |
佐藤 常雄 |
㈱錢高組 |
| 〃 |
細田 泰宏 |
大成建設㈱ |
| 〃 |
日吉 直 |
㈱ダイヤコンサルタント |
| 〃 |
山本 光起 |
㈱竹中工務店 |
| 〃 |
春木 隆 |
㈱竹中土木 |
| 〃 |
依田 眞 |
中部電力㈱ |
| 〃 |
田仲 昶三 |
帝石削井工業㈱ |
| 〃 |
粕谷 太郎 |
鉄建建設㈱ |
| 〃 |
畑野俊一郎 |
東急建設㈱ |
| 〃 |
鈴木 護 |
東洋エンジニアリング㈱ |
| 〃 |
川西 龍一 |
東洋建設㈱ |
| 〃 |
是枝 信也 |
西松建設㈱ |
| 〃 |
見満 好則 |
日揮㈱ |
| 〃 |
渡辺 英市 |
日石エンジニアリング㈱ |
| 〃 |
菊地 慎二 |
日本国土開発㈱ |
| 〃 |
五十嵐義則 |
能美防災㈱ |
| 〃 |
田中 正 |
ハザマ |
| 〃 |
清水 賀之 |
日立造船㈱ |
| 〃 |
橋場 弘道 |
日立電線㈱ |
| 〃 |
浅見欽一郎 |
日立プラント㈱ |
| 〃 |
水谷 敏彦 |
㈱フジタ |
| 〃 |
新貝 和照 |
富士電機㈱ |
| 〃 |
関 順一 |
前田建設工業㈱ |
| 〃 |
波多腰 明 |
三菱重工業㈱ |
| 〃 |
大月 一史 |
村本建設㈱ |
| 事務局 |
早川 雅彦 |
地下センター |
(敬称・役職略)

■地下開発利用研究センター調査研究組織図■
平成9年度の調査研究組織は以下のとおりです。
(平成9年8月末現在)
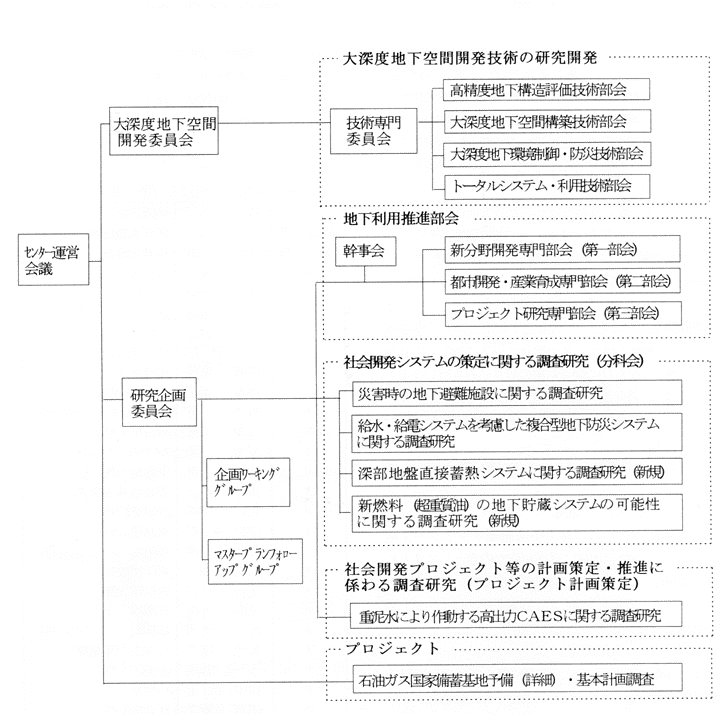

■会員の皆様へのお知らせ■
○第194回サロン・ド・エナ開催のご案内
日 時 : 平成9年9月17日(水)17:30~
講 師 : 釣谷 康 殿(運輸省運輸政策局 技術安全課長)
テーマ : タンカー油流出事故への対応と課題 ~ナホトカ号及びダイヤモンドグレース号の事故を踏まえて~

|