
第21号/1991.5
■就任の挨拶
■GEC成果発表会’91開催のご案内
■株式会社ミツトヨ地下研究棟見学記
■新聞記事から
■会員の皆様へのお知らせ
■就任の挨拶■
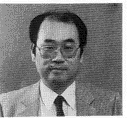 通商産業省立地公害局 産業施設課長 河野修一氏
通商産業省立地公害局 産業施設課長 河野修一氏
就任にあたりましてご挨拶させていただきます。
人類の歴史において、新しい時代が切り拓かれた時期には、先端技術に裏付けられたフロンティアの開発が重要な要素になっています。例えば、羅針盤技術により可能になった外洋航海が新大陸の発見をもたらし、蒸気機関車等の動力技術がアメリカ大陸の開発を可能としてきました。また、これらのフロンティアを開発した国家は、その開発によって得られた果実等を糧とし発展してきました。別な言い方をすれば、フロンティア開発は人類の進歩と繁栄に不可欠の事業なのです。
ところで、現在の地下開発は、開発コストの高さ、開発期間の長さ、安全性確保の困難さ、地質状況把握の困難さ等の理由により、地価の高い大都市部や寒冷地での地下鉄、地下街としての利用や上水道、下水道、電線等の埋設利用に限られており、大深度地下はもちろん浅深度地下もほとんど未開の状態にあるといえます。すなわち、地下は、多くのフロンティアが開発されつくされた現代において、残されたフロンティアであります。
このようなことから、地下は、宇宙、海洋と並び次の世紀を担うフロンティアとして、人類が夢をもって、開発に取り組むべき重要な空間であると考えます。
特に、我が国においては、今後社会資本の整備に力が注がれることが予測されますが、その際、社会資本整備のための空間として、地下空間が切り札的存在になると思われます。そして、これを支えるキーテクノロジーがジオ・ドーム開発技術等の革新的な地下開発技術ではないでしょうか。
このような時期に、会員の皆様方が、地下開発に関係する企業の集まりとして地下開発利用研究センターを開設し、地下開発にかかわる技術開発や調査研究など種々の活動を行っておられることは極めて意義深いことであると考えます。
今後とも、多岐にわたる会員の力を結集し、積極的な研究活動、技術開発に取り組んでいただくことを希望いたしまして、就任の挨拶とさせていただきます。

■GEC成果発表会’91開催のご案内■
当協会では、昨年度から新しい試みとして、年度ごとに当協会において活動した各委員会における成果の発表会を開催していますが、今年度から当地下センターの活動についても発表することとなりました。下記のとおりご案内いたしますので、会員各位の多くのご参加をお待ちしています。
| <開催日> |
平成3年7月17日(水)、18日(木) |
10:00~17:00(本部) |
|
7月19日(金)、 |
10:00~17:00(地下センター) |
<場 所>機械振興会館ホール 地下2階
<会 費>無 料
<定 員>250名
<申込方法>5月末賛助会員窓口宛開催案内及び申込書を送付させていただきます。
★★★プログラム概要★★★
<7月19日(金)>
| 10:00~12:00 |
「マスタープラン専門委員会成果-基本問題部会及び利用施設系部会-」 |
|
委員兼幹事長 石崎 秀武 (清水建設㈱) |
|
委員兼幹事長 岩崎 賢二 (東京海上火災保険㈱) |
|
委員兼幹事長 吉井 茂雄 (大阪ガス㈱) |
|
委員兼幹事長 高瀬 陽平 (石川島播磨重工業㈱) |
|
委員兼幹事長 大野 義郎 (NHK) |
| 13:00~14:00 |
「人・物の高速垂直連続輸送システムに関する調査研究」 |
|
委員兼作業部会長 関口 一夫 (富士電機㈱) |
| 14:00~15:00 |
「地下空間を活用した地区再開発システムに関する調査研究」 |
|
委員兼作業部会長 大塚 光正 (梶谷エンジニア㈱) |
| 15:00~16:00 |
「地下清掃工場システムの調査研究」 |
|
委員会幹事 内藤 和章 (㈱大林組) |
| 16:00~17:00 |
「通産省大型プロジェクト-大深度地下空間開発技術」 |
|
技術開発第2部長 奈良 俊勝 (ENAA、GEC)、他 |

■株式会社ミツトヨ地下研究棟見学記■
4月19日(金)日刊工業新聞の「リニアスケールは、地下から生まれました。」の広告に好奇心を刺激されて広告主の株式会社ミツトヨ様の御好意により全国的にも稀少な地下研究棟を見学させていただくこととなった。
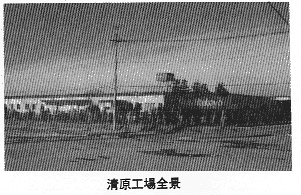
|
見学先
|
株式会社ミツトヨ
清原工場 超精密スケール研究棟
栃木県宇都宮市清原工業団地24
|
|
地下研究棟規模
|
深度11m(G.L.9m)天井高3.5m
土被り2.5m 面積775.2㎡
|
|
工 期
|
昭和62年3月~9月
|
JR宇都宮駅から車で約15分のところにミツトヨ清原工場はあった。30以上の会社の工場・研究所がある工業団地内は緑が多く、団地内で働く人達のた
めに体育館やプロ野球も開催される立派な野球場もあり羨ましいばかりの環境だと言える。
清原工場に到着すると、まず会議室で会社案内のビデオを見た。精密測定機器の総合メーカーとしてマイクロメータの国産化に始まり、半世紀を過ぎた今、エレクトロニクス等の最先端技術を駆使した製品を世界120カ国以上に送り出しているとのことである。
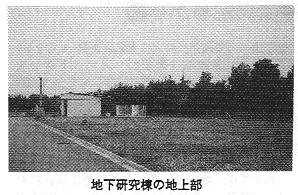 ビデオを見た後、まず地上の工場棟から見学させて頂いた。超精密な技術を要するスケールの製作には温度、湿度、気圧に細心の注意が払われる。特に温度については1度の差がガラス1mについて8.5μmの誤差が生じるため、基準温度である20℃をできるだけ保つことが良質のスケールを作る鍵になる。正にミクロの世界である。従って工場棟内は周囲を廊下にしており外部の温度等による環境変化の影響を少なくするよう工夫がされている。スケールの製造工程についての説明を受けた後、いよいよ地下研究棟の見学である。
ビデオを見た後、まず地上の工場棟から見学させて頂いた。超精密な技術を要するスケールの製作には温度、湿度、気圧に細心の注意が払われる。特に温度については1度の差がガラス1mについて8.5μmの誤差が生じるため、基準温度である20℃をできるだけ保つことが良質のスケールを作る鍵になる。正にミクロの世界である。従って工場棟内は周囲を廊下にしており外部の温度等による環境変化の影響を少なくするよう工夫がされている。スケールの製造工程についての説明を受けた後、いよいよ地下研究棟の見学である。
地下研究棟の内部環境
室温:20℃(±0.2℃) 湿度:45%(±10%) 空気清浄度:クラス100
|
エレベーターで地下に降り連絡通路(約15m)を進むとめざす地下研究棟に到着した。空気は涼しく感じられ肌に気持ち良い。また廊下にも音楽が流れており、窓がない環境を補っているようだ。この研究棟では超精密スケールの製作及びスケールの測定の他、様々な実験を行うため、より安定した環境が要求されるので、幾重にも囲い順次温度管理され、最終的に温度は0.001℃の精度で管理され作業が行われている。(従って廊下から実験室等の内部を見るだけである。)
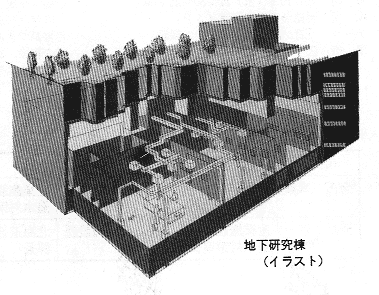 地下立地の主な理由は地下が外部の影響を受けにくいこと(宇都宮周辺は雷がよく発生するように気圧の変化も大きい。またこの研究棟は一般道路からも離れた位置にある。特に地下6m以深は地中温度が日変化、年変化共にほとんど影響を受けないことが大きい)また研究棟建設のため最深部で14~15mまで掘削したが、地下水がまったく出なかったことなどが挙げられる。研究棟内では、極力内部の発熱をなくすため地上の光源から光ファイバーで光を取り込み、熱源(赤外線等)を取り除いた冷光を使用している。
地下立地の主な理由は地下が外部の影響を受けにくいこと(宇都宮周辺は雷がよく発生するように気圧の変化も大きい。またこの研究棟は一般道路からも離れた位置にある。特に地下6m以深は地中温度が日変化、年変化共にほとんど影響を受けないことが大きい)また研究棟建設のため最深部で14~15mまで掘削したが、地下水がまったく出なかったことなどが挙げられる。研究棟内では、極力内部の発熱をなくすため地上の光源から光ファイバーで光を取り込み、熱源(赤外線等)を取り除いた冷光を使用している。
このような内部環境維持のおかげで世界にも通用する超精密なスケールができるのだ。来た経路を戻り地上に出ると、地下研究棟の上部も見せて頂いた。テニスコートの横の芝生の部分がそれだった。この芝生の下にまさか世界的にも誇れるスケールの研究棟があるとは知らない人は決して気付くまい。
他に先がけて地下の特性を生かしたこの地下研究棟は進取の企業精神を反映しているように感じ、「マクロ」な地下開発がミクロの世界でも役立つ可能性を認識すると共に、ご多忙にもかかわらずご案内いただいた株式会社ミツトヨの皆様に感謝しながら清原工場を後にした。

■新聞記事から■
○地下道が「美術館」に(日本経済新聞 4月6日)
東京都西新宿の「新宿プロムナードギャラリー」がオープン。都が都庁の移転に伴って建設した歩行者用地下道「ワンデーストリート」(全長433m)の一角。地下道の壁面に現在絵画16点を陳列。地下道の利用者には好評。
○廃鉱を利用して「雲をつかむ研究」本格化(日刊工業新聞 4月8日)
昨年5月、産学官からなる「雲物理現象研究会」が発足。北海道上砂川町の三井石炭鉱業上砂川鉱の縦坑を利用した実スケールの人工実験・研究計画を提案。雲の様々な現象解明は地球温暖化や酸性雨など環境問題の解決にも役立つと考えられている。
○東京都、地下都市計画のパイロットプラン策定(日刊建設工業新聞 4月10日)
東京都都市計画局は、今夏にも掲記プランを策定し、区市町村への説明に移る方針。統一的なコンセンサスを得た後、個々の地域を指定し、本格的な地下都市計画策定へ発展させる見通。
○都と台東区、上野一帯に地下道(日本経済新聞4月10日)
JR上野、御徒町周辺に、地下の歩行者交通ネットワークを作る。同時に地下駐車場地下広場も整備し、地上の交通全般の混雑緩和を目指す。
96年度都営地下鉄12号線の開業までに完成させる予定。
○アンコール遺跡の倒壊、地下水位変動が原因(日本経済新聞 4月12日)
カンボジアのアンコール遺跡を守ろうと現地調査を続けていた「第5次上智大学アンコール遺跡保存修復国際調査団」が調査結果の概要を発表。ボーリングした結果、地下水の水位が上昇したり、下がったりしていることが倒壊の原因と判明。
○地下に鋳物研究所(日経産業新聞 4月24日)
東急不動産など3社は7月、埼玉県川口市で金属鋳物の研究所を地下に設けた超高層マンションの建設に着手。
平成5年12月に完成、総事業費は約95億円。
○地下3000m級井戸を掘削(日本経済新聞 4月26日)
科学技術庁など7省庁は首都圏直下型大地震予知体制強化のため東京湾岸に地下3000m級の観測用井戸を掘削することを決定。91年度に4億円かけて用地を確保、掘削を開始する。
○建設残土を再利用へ、6月に三セクを発足(日刊工業新聞 4月26日)
公共事業から発生する残土を民間の宅地造成事業などに供給する第三セクター「首都圏建設資源高度化センター」(仮称)の設立発起人会が開催。出資者を募集し、6月上旬をめどに設立総会を開き新会社を設立する予定。資本金は30億円。

■会員の皆様へのお知らせ■
○サロン・ド・エナ(第126回)開催案内
| 1.日 時 |
6月19日(水)17:30~20:00 |
| 2.場 所 |
当協会AB会議室(4F) |
| 3.テーマ |
「日ソ経済協力の現状と課題」 |
| 講 師 |
江部 進氏 (日ソ経済委員会事務局次長) |
○欧米における地下環境制御・防災対策技術調査報告書(平成2年度)完成
昨年(平成2年11月)実施した上記調査団の報告書ができあがりました。
ご協力いただいた参加者の皆様、ありがとうございました。
参加者以外の購入希望者には実費にて配布いたしますので申込みは地下センター中村までお願いいたします。
○人事異動(通商産業省)<4月15日付>
|
氏 名
|
新
|
旧
|
|
余田 幸雄
|
大臣官房付
|
産業施設課長・(併)産業施設課
造水対策室長
|
|
河野 修一
|
産業施設課長・(併)産業施設課
造水対策室長
|
北海道通商産業局総務企画部総務課長
|

|