
第172号/2004.1
■地下利用推進部会活動報告
経済産業省地域経済産業審議官 平井 敏文 氏
平成16年の新春を迎え、謹んでお慶びを申し上げます。新しい年の門出にあたり、地域経済産業政策に対する所感を述べさせていただきます。
日本経済全体の状況は、輸出や設備投資の増加に伴う生産の持ち直し、大企業を中心とする収益の増加など回復傾向にありますが、各地域の景況は、個人消費の回復力も未だ弱く、工場の海外移転による空洞化や、高い失業率など、依然として厳しい状態が続いております。
日本経済全体の本格的な回復は、地域経済の活性化とその基調の定着があって初めて実現されるものと考えます。地域経済産業グループは、各地で地域の活性化のために燃える人たちとともに、産業クラスター計画の推進等の各般の施策を充実させ、マクロ経済の閉塞感をミクロの活力で打ち破るべく、地域経済の再生に全力で取り組んでまいります。
「産業クラスター計画」の目的は、地域に集積する中堅・中小企業、大学、金融機関、商社等の人々の現場主義に立脚し、フェイストゥフェイスを基本とする活発な交流によって、共同の技術開発や新事業展開等を図る新たな産業集積(産業クラスター)を形成することにあります。そのため、北海道から沖縄まで日本各地に配置された8局1部の地域経済産業局の職員2200名が、各種の政策ツールを総合的に活用し、それぞれの地域に密着した施策を実施しております。具体的には、産学官の広域的な人的ネットワークの形成と、地域の特性を活かした実用化技術開発の支援、起業家育成施設(ビジネス・インキュベータ)の整備等インキュベーション機能の強化を、総合的・効果的に推進しております。
計画も2年半を過ぎ、着々と成 果を見せつつあります。まず、産 学官の人的ネットワークは、全国 の産業クラスター計画19プロジ ェクトで約5000社の中堅・中
小企業と、約200もの大学が参 加するまでに拡大しました。また、 全国の経済産業局の職員が企業経営者や研究者のもとを訪問し、緊密に意見交換をすることにより、技術開発ニーズの把握や産学協同の技術開発の働きかけ、企業の課題に対応した支援策の活用支援、専門家の紹介などを進めております。こうした人的ネットワークの強化策により、ネットワーク内での技術・経営情報・販路などの経営資源が有機的に結合され、産業集積の苗床が出来上がりつつあります。
日本の各地域により多くの産業の集積が形成されるためには、地域の方々の自発性と協力はもとより、長い時間と地道な努力・忍耐力が必要とされます。現場の企業経営者や技術者の方々、また、自治体や経済団体、大学、研究機関等のみならず、住民の方々を含め、地域の活性化を目指す人々と共に力を合わせて「産業クラスター計画」を、地域再生と日本経済の発展の核としてこれからも鋭意進めていきたいと考えております。
最後に、本年も地域経済産業政策への御理解と御協力をお願いするとともに、皆様の御多幸と御健勝を祈念いたしまして、新年の御挨拶とさせていただきます。
地下情報化部会(吉村和彦部会長)では、地下利用事例の調査として、10月31日に、神奈川県葉山町の葉山浄化センターを取材しました。
葉山町は、「美しい水環境を次の世代に引き継ぐ下水道」というスローガンを掲げ、公共下水道事業に取り組んでいます。葉山浄化センターは、海岸付近の景観(観光資源)の保全、河川水量の確保などを目的に、葉山町の北部、標高約50mの山間部に建設された地下(トンネル)式の下水処理場との説明を受けました。約7年間の工事を終えて、平成11年3月に運用を開始しました。
汚水の処理方法は、生活排水などの汚水を沿岸部にあるポンプ場に集め、それを圧送管で、総延長約4.7km、高低差約35mを約半日かけて、上流部にある浄化センターまでポンプ圧送し、酸素活性汚泥法により処理しています。浄化された水(BOD:1ppm以下)は、透明度もかなり高く、きれいな水となって河川に放流されます。
この下水道の管渠は、内径約2mで上半分が生活排水を自然流下するために使われ、下半分に汚水を圧送するための圧送管(直径約45cm)が2本設置してあるという、珍しい構造となっています。
運転管理は、監視室で集中管理されており、24時間の自動運転が行われています。また、水処理を行うエアレーションタンクは密閉式であり、ほとんど臭いは感じませんでした。
汚泥管理棟以外のほとんどの施設は、地下に作られており、地上からでは想像できないほど広い空間が地下に広がっていました。
浄化センターの主な諸元(認可上H15.3.31現在)を以下に示します。
・処理能力:日最大汚水量(12,400m3/day)、処理人口(17,800人)、処理面積(300ha)
・方式:排除方式(分流式)、処理方法(酸素活性汚泥法)
・構造:鉄筋コンクリート造一部鉄骨鉄筋コンクリート造、地上3階、地下3階
・地下トンネル:空洞形状(幅約20m×長さ約61m×高さ約22m)を現在2本設置
最後に、今回の取材調査に際して、ご協力いただきました葉山浄化センターの方々を始め、関係者の方々に御礼申し上げます。
(前田信行 記)
水処理施設(地下トンネル内) 浄化センター入口にて
□地下環境部会施設調査報告(豊島・直島産業廃棄物処理施設見学)
当部会では企業及び自治体系公共事業者の土壌・地下水汚染対策の実態調査を実施しており、その一環として11月6日、7日の両日、香川県豊島/直島の産業廃棄物の現地調査を実施しました。
豊島は大量の産業廃棄物(67万トン)が不法投棄され、マスコミでも社会問題として大きく取り上げられています。長年にわたり県と住民との間で争われたこの豊島問題は2000年6月に公害調停を経てようやく解決に至り、約10年間で産廃物は撤去・処理される予定です。
現在豊島の産廃物は2003年3月に完成した保管/梱包設備・特殊前処理物処理施設他等で処理されたのち、専用輸送船で8㎞離れた直島に海上輸送(300T/日)されます。豊島から直島に運ばれた産廃物は、2003年9月に運転をスタートした新設の中間処理施設で焼却・溶融処理され、また処理の過程で発生する副成物の溶融スラグ等は骨材などに有効利用されます。
これら産業廃棄物処理に要する事業費は約500億円(10年)とのことでした。
1.豊島廃棄物処理施設概要及び対策
実際の現場で見ると産廃物は、10階建てのビルが幾つも入ってしまうほどの大量のものであることに驚かされました。汚染防止対策としてダイオキシンその他の有害物質の流出や浸水を防止するため遮水壁(長さ360m、深さ2~18m)の設置、廃棄物の飛散防止、雨水の流入排除のための遮水シートの敷設、汚染拡大防止のため廃棄物の移動などの措置が取られていました。また、直島での産廃処理を効率的に進めるため産廃の選別、岩石・金属の粉砕処理をする特殊前処理施設及び保管・梱包施設等が設けられています。また、地下水・侵出水浄化のための高度排水処理施設(65T/日)が設置されています。
2.直島中間処理施設概要及び対策
三菱マテリアル直島精錬所構内の小高い丘の上に新設の直島中間処理設備があります。豊島から海上輸送された廃棄物等は直島町の一般廃棄物と共に同設備で焼却・溶融処理されます。鉄や岩石の付着可燃物を焼却するロータリーキルン炉(24T/日)及び日本で最大といわれる回転式表面溶融炉(100T/日×2基)が設置され、約1300℃の高温で溶融処理されるためダイオキシン類は完全に分解されるとのことでした。
また、溶融処理に伴い発生する飛灰やスラグ等の副成物を再資源化し有効利用すること以外にも、プラント排水や雨水を再利用するなど環境面に配慮された完全循環型の施設でした。
日本最大の産業廃棄物不法投棄現場と処理施設等の今回の見学は、生きた教材として今後の産業廃棄物の問題、土壌汚染問題等々を考えていくうえで非常に参考になりました。
最後に、今回の施設見学に際して、ご協力いただきました県直島環境センター片山氏始め関係者の方々に厚く御礼申し上げます。 (前田秀穂 記)
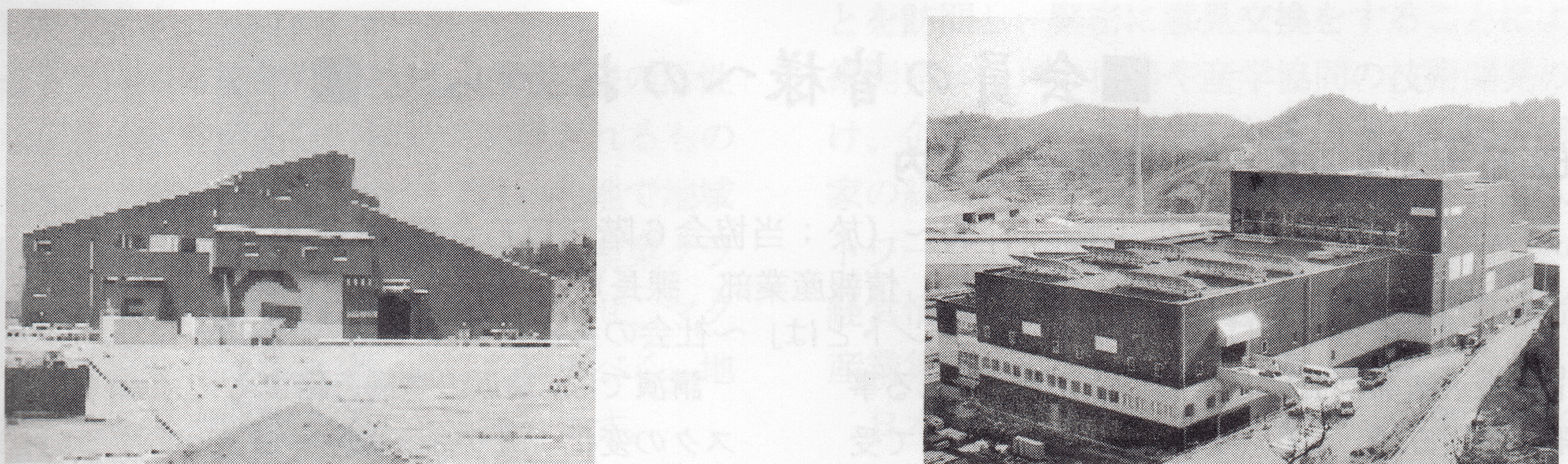
豊島保管・梱包施設 直島中間処理施設
□都市競争力部会首都高速中央環状新宿線見学会報告
シールド機(代々木シールド) 内廻り線の状況(中野坂上)
□第262回サロン・ド・エナ開催のご案内
日 時 :平成16年1月21日(水)17:30~(於:当協会6階CDE会議室)
講 師 :辻村 亨 氏(東京海上火災(株)情報産業部 課長)
テーマ :「企業経営におけるリスクマネジメントとは」~社会の多様化の中で企業に求められるものは~
講演趣旨:最近新聞紙上等で大きく取り上げられる事故が多発しているが、これらを「他人ごと」として受けとめるだけでなく、自社の経営への影響という観点でみる必要性が高まっています。
講演では、最近の事例を踏まえ ①企業を取り巻くリスクの変化 ②リスクをマネジメントする経営の必要性 ③リスクにどう対処すべきか について、具体的なお話をして頂きます。(講演終了後懇親立食パーティ)
会 費:3000円(非会員5000円)(当日受付にて申し受けます)
申込要領:FAXで事務局へお申し込み下さい。申込多数の場合は先着順で締め切らせていただきます。
地下開発利用研究センター 事務局 中村 (TEL:03-3502-3671/FAX:03-3502-3265)
* 地下センターのホームページ(http://www.enaa.or.jp/GEC/)の「お知らせ」の「催物案内」から直接
申込みもできます。
|
舌句雑感:"100万分の1グラムの歯車を見ましたか" 直径0.14mm、100万分の1グラムのプラスチックの歯車を見たことがありますか?私は見ましたが、肉眼ではゴミとしか見えませんが、本当の歯車の形をしています!!■松浦さんが社長の樹研工業という社員90名の小さな会社が作ったものですが、用途は今のところなし。作りたいから作ったとのこと。この極小の歯車をつまむピンセットを大学の先生が半年かけて開発したそうです。■この会社は、先着順採用、定年制なし、タイムカードなし、仕事は自己責任で等のユニークな経営でも話題になっています。■日本の中小企業の製造業の中には、こんな面白い会社がいっぱいあります。本当に捨てたものじゃないなと思います。お互いにがんばりましょう!□舌句雑感、あまり変わってないじゃないかと思われた方もあると思いますが、事情により、あと少し編集を続けることになりました。再度よろしくお願いします。 (GECニュース編集者)
|