
第14・15合併号/1990.10.11
■委員会報告
■ヨーロッパにおける地下開発利用実態調査にあたって
■大型プロジェクト見学記
■会員の皆様へのお知らせ
■委員会報告■
10月に開催された主な委員会、会議とその主な内容は以下の通りです。
マスタープラン専門委員会(第4回)
| 日時: |
10月16日(火)10:00〜12:00 |
| 議題: |
① 基本問題部会及び利用施設系部会進捗報告
② 基盤系技術部会の進め方について
③ その他
|
来賓の余田通産省産業施設課長より挨拶があり議事に入った。前回の専門委員会で報告の大綱が審議された報告書(その1)「地下空間開発利用の現況調査」の印刷ができあがり石崎幹事長よりその紹介と全体報告があった。また、マスタープラン策定のステップ2となる平成2年度の調査研究のまとめ方について幹事長及び各部会長より説明があり、これに対して学識委員より質問と有益なコメントがあった。また、ステップ3に取り組むための基盤技術系4部会の編成案と募集計画について審議・承認された。
研究企画委員会(平成2年度第3回)
| 日時: |
10月17日(水)13:30〜15:30 |
| 議題: |
① 平成2年度事業進捗報告
② 平成3年度補助金要望について
③ その他
|
来賓の通産省立地公害局仁賀課長補佐より挨拶があり議事に入った。
事務局より平成2年度のマスタープラン策定についてその進捗状況(ステップ2)及び基盤技術系4部会(ステップ3)の委員募集計画につき報告があり了承された。地下センター関係の平成3年度補助金要望案について山口専務理事より説明があり了承された。これには運営資金に対する補助金のほか、マスタープラン策定、研究開発6テーマ、実証実験1テーマ等の事業費に対する補助金が含まれている。
次いで、新たに「地下清掃工場システム」についての分科会を発足することが提案され承認された。また、当センターの事業活動について検討するワーキンググループを発足させることになった。そのほか、9月に実施された海外調査について事務局より報告があった。
センター運営会議(平成2年度第2回)
| 日時: |
10月22日(月)15:00〜16:40 |
| 議題: |
① マスタープラン専門委員会進捗状況報告
② 分科会活動進捗状況報告
③ 平成3年度補助金要望について
④ 通産省大型プロジェクト進捗状況報告
⑤ その他
|
来賓の通産省立地公害局産業施設課仁賀課長補佐より挨拶があり議事に入った。
山口専務理事よりマスタープラン策定及び分科会活動による研究開発について平成元年度の成果報告書及び平成2年度の進捗状況について報告がされた。また平成3年度の補助金要望については運営資金及び地下空間利用策定の事業費の補助金(1億6,492万円)の要望を10月末日までに日本自転車振興会に提出することが承認された。また新しい分科会「地下清掃工場システム」の発足、大型プロジェクト等の受託研究の進捗状況について報告があり了承された。
大プロ・技術専門委員会(第3回)
| 日時: |
平成2年10月30日(火)10:00〜11:30 |
| 議題: |
① 平成2年度委託業務(NEDO)中間報告
② 平成2年度新型負荷平準化電源環境影響評価技術調査(NEF)について
③ 平成3年度研究開発予算概算要求について
④ 研究開発業務記録映画(ビデオ)について
⑤ その他(他委員会状況報告等)
|
来賓として出席された工技院・大プロ室、倉研究開発官より挨拶があり議事に入った。事務局より平成2年度委託業務の中間報告として、ほぼ順調に進捗していること、平成2年度新型負荷平準化電源環境影響評価技術調査が、NEFより新たに委託を受けたことの報告があった。また、平成3年度研究開発予算概算要求については、既に全体を取りまとめて工技院に提出したが、関係各社の役員には通産省に対し陳情をお願いし、席上、山口専務よりお礼を申し上げる旨の発言があった。研究開発業務記録映画(ビデオ)については、事務局より本研究開発の記録を映画(ビデオ)として残すか否か等について検討を行うためワーキンググループを設置する事が決定された。ワーキンググループからの答申を得て当委員会及び大深度地下開発委員会の審議を経て最終決定されることとなる。

■ヨーロッパにおける地下開発利用実態調査にあたって■
地下センターでは、大深度の地下開発のみならず、広く地下空間開発利用の実態を調査するために、平成2年度事業の一環として、地下空間の開発利用では先進的な位置づけにあるヨーロッパにおける実態を調査することを目的として、調査団を派遣することにした。
調査団は、東京大学工学部教授小島圭二氏を団長として総勢31名が、Aグループ、Bグループにわかれ、ストックホルム市都市計画室の視察プログラムによる地下施設の見学の後、Aグループによる北欧において開催された国際会議「Urban Underground Planning(都市における地下計画)」への参加と、Bグループによるオスロ市地下上水道施設並びに地下スポーツ&スイミングセンター等の見学、及びドーバー海峡ユーロートンネル工事地下現場(英国側)見学を行い、再びA、B両グループ合流しての西独CAES利用発電所等の見学、フランスとベルギー国境近くにある地下原子力発電所、及びルーブル美術館地下施設等の見学を行った。
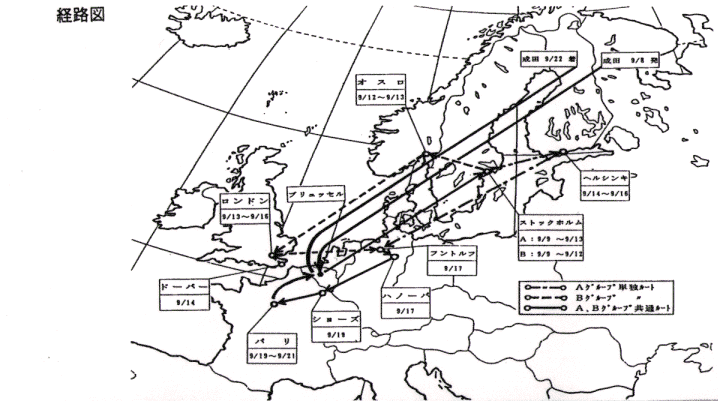

(国際会議について)
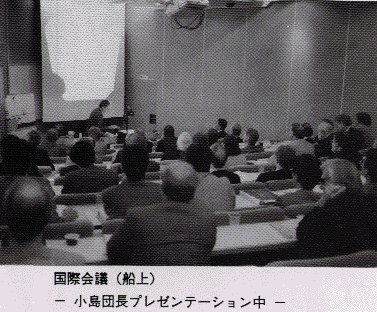 当国際会議は6つもの団体、―ストックホルム市、ヘルシンキ市、ストックホルム州会議、フィンランド環境省、スウェーデン都市国家計画協会、それにIFHP―により開かれた。また、2つの国の2つの都市を結んで、一つの会議が開かれることは大変珍しいことである。
当国際会議は6つもの団体、―ストックホルム市、ヘルシンキ市、ストックホルム州会議、フィンランド環境省、スウェーデン都市国家計画協会、それにIFHP―により開かれた。また、2つの国の2つの都市を結んで、一つの会議が開かれることは大変珍しいことである。
国際会議の印象は、どちらかというと企画的、問題指摘的なものが多く、それだけ地下利用開発については、種々難しい問題もあり、対応の仕方に多様性があるという印象を受けた。しかし、各国とも、各種環境問題を真面目に考えており、日本も今後この点については世界と協力していく必要性を感じた。特に、日本における現在の地下利用計画は、地上の代替としての位置付けが大きいように思えるが、この環境保全という命題は、地下の持つ最大のメリットとして、打ち出していくべきものであると感じる。また、地下利用については、やはり国家規模でその方針を定め、国、地方自治体の強力なリーダーシップ(特に計画面、規制面において)、経済支援および民間資本の積極的な活用無くしては、なかなか成就しない気がした。(研究も含め)
国際会議日程
日時
場所 |
テーマ
|
議長(主な発表者) |
9.12
ストックホルム市
|
地下建設の可能性と制限
(地下計画・北欧の地質・人に対するデザイン
経済性・近未来地下建設の方向)
|
Jeno Vitsen
(Hans E. Vohlin
John Carmody) 他3名
|
9.13
ストックホルム市
|
地下利用の現在の進展状況
(下水処理・病院・熱エネルギー貯蔵
高圧ケーブル・地下水・地下鉄)
|
Bo Vijkmark
(Nils Friedrich
Bjorrn Flodstrom) 他4名
|
9.13
(船上)
|
ワークショップ
(日本・オランダ・香港・スペイン各国における
地下開発構想例)
|
Gustaf Landahl
(小島 圭二
D. J. Howells)他5名
|
9.14
ヘルシンキ市
|
情報システム
(IFHPの紹介・地下データの収集調整
地下マッピングとデジタル情報システム)
|
Martti Koivumaki
(Jon H. Leons
Usko Anttikoski)他2名
|
9.15
ヘルシンキ市
|
計画と規制
(地下建設・所有権・新立法要求事項・建設
許可と検査・地下アメニティ・情報・新形態)
|
Lars Hedman
(Lars Hedman
Jaakko Stauffer) 他5名
|
(施設調査について)
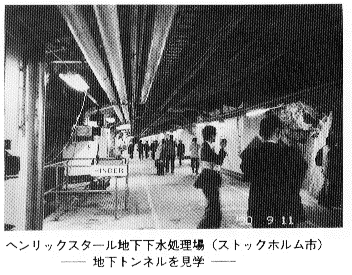 下水処理、大深度地下鉄、地下研究室など北欧の地下開発は、足が地についている感じを受けた。
下水処理、大深度地下鉄、地下研究室など北欧の地下開発は、足が地についている感じを受けた。
これらは北欧特有の自然環境(酷寒)からの自己保全、外部から身を守るといった必然性があり恵まれた地質の上で成されたものであり、現在も引き続き地下空間利用の拡張工事が進められている。
核シェルター、地下原子力発電所のように時代の要請に基づいてなされた地下空間利用は、開発当初は確かに理想的理念の下に当時の最高の技術を駆使してなされ、将来技術の進歩への貢献と社会活動への波及効果上大きな意味を持っていた。
しかし、世界をとりまく環境の変化により、その効用が制限される一方、維持管理面の負担が大きくなっている。地下建造物は一度建造すると作り直しが困難である。長期的展望にたった計画の必要性を実感した。
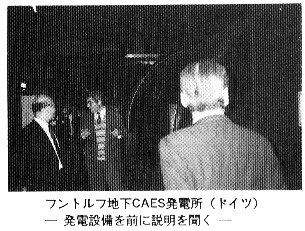 過密化した都市においては、スペース確保難の条件下で、交通・物流施設の拡充が求められ、地下の有効利用が図られる。オスロ市ではシェルター機能を持った地下鉄が建設されていた。また、地下自動車専用道路も充実していた。
過密化した都市においては、スペース確保難の条件下で、交通・物流施設の拡充が求められ、地下の有効利用が図られる。オスロ市ではシェルター機能を持った地下鉄が建設されていた。また、地下自動車専用道路も充実していた。
安全確保のための諸システム、トンネル内空気の浄化施設、都市内渋滞を緩和すると共に新道路建設費を捻出するための料金徴収制度など、当該施設建設の先進都市として北欧都市から学ぶものは多かった。
フォーラム・レ・アールやルーブル美術館では、地上空間の利用(高層化)が制限された状況下で、地下が開発された。町並み保存の都市計画の観点から地上空間開発を制約された都市部における、このような地下開発は今後とも多いと思った。また、ハノーバー地下街でも共通するが、人の多く集まる地下空間では、中央部のオープンカット空間が地下の閉塞感を大幅に緩和する、との実感を得た。
調査施設一覧表
日時
場所 |
調査施設名称
施設の概要
|
・調査アポイント先
・案内者
(所属組織) |
9.11
ストックホルム市 |
ヘンリックスタール地下下水処理場
岩盤内にトンネルを展開して、下水処理場を建設。壁面はほとんど素掘りのまま。
|
・ストックホルム市都市計画局
・ストックホルム下水道局 |
9.11
ストックホルム市
|
クララ教会地下シェルター兼駐車場
教会の下のシェルターで平和時には駐車場。
15,000人を収容、1955年着工、1960年稼動。
|
・ストックホルム市都市計画局
・ストックホルム市消防隊 |
9.12
オスロ市
|
オセット地下上水道処理施設
岩盤内の処理場で、湖水をトンネルで取水。
建設費は掘削岩の売却で賄えたとのこと。
|
・在日ノルウェー大使館
・技術担当者 |
9.13
オスロ市
|
ホルムリア地下スポーツ施設兼シェルター
丘の中腹からトンネルを掘りシェルターを建設、平時用にアスレチックジム、プール、等を併設。
|
・在日ノルウェー大使館
・技術担当者
|
9.13
オスロ市
|
オスロ地下自動車専用道路
(交通渋滞解消用)新道路の70%はトンネル。
トンネル内空気浄化装置で大気汚染も緩和。
|
・在日ノルウェー大使館
・施設調査官
|
9.14
イギリス
|
ドーバー海峡ユーロ・トンネル
ドーバー海峡下、全長50kmの海底トンネル。
鉄道トンネル(2本)とサービストンネル(1本)。
|
・ユーロトンネルグループ社
(社長、融資担当部長)
・同社技術担当者、他
|
9.17
ドイツ
|
フントルフ地下CAES発電所
岩塩層を真水で溶解して形成した空洞に圧縮空気を貯蔵する圧縮空気貯蔵発電所を建設。
|
・プロイセン電力株式会社
・施設維持管理担当者
|
9.17
ドイツ
|
ハノーバー市地下繁華街
オープンカット方式の地下街。中央は人の通路、両側にショッピング街を配置。
|
・ハノーバー市市役所
・ハノーバー市地下担当主任
|
9.19
フランス
|
ショーズ地下原子力発電所
山の中腹から3本のトンネルを掘り、地下空間に空洞を設け、原子炉を格納。
|
・在日フランス大使館
・施設管理担当者
|
9.20
パリ市
|
フォーラム・レ・アール市場跡地の地下開発
市場跡地を再開発し、交通ターミナル、ショッピングセンター、文化施設等を建設。
|
・アポイント無し (自由視察)
・通訳が同行
|
9.20
パリ市
|
ループル美術館の地下空間利用
スペースを拡張するため、入場口にガラス張りピラミッドを設けた地下空間を開発。
|
・J. C. DOMONT、他
・建設技術者 施設管理担当者
|
(雑感)
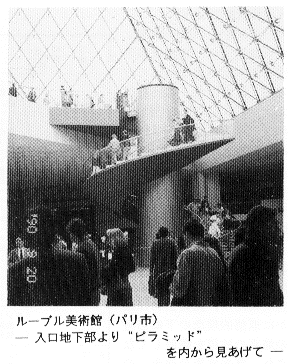 最初の訪問地・ストックホルムは小雨に煙る初秋の日曜日の昼下がりであった。
最初の訪問地・ストックホルムは小雨に煙る初秋の日曜日の昼下がりであった。
調査旅行期間中、幸いにも天候に恵まれたが、この日は雨に降られた数少ない1日であった。ストックホルムは、地表の50cm下はすべて岩盤層とのことで、これをうまく利用した大空洞の地下シェルターや、地下鉄等の地下施設の建設が大変進んでいるのを実感することができたが、地上の施設においても、毎年ノーベル賞受賞者を集めての晩餐会が開かれると言う市庁舎の一室は、特に印象に残るものの一つであった。
ストックホルムで3泊の後、Aグループは国際会議出席のため、引き続きストックホルム、そしてヘルシンキへと。Bグループはオスロ、そしてロンドンへと暫しの別れとなった。再び合流したのは、旅行も半ばの日曜日の午後、ブレーメンのホテルであった。
ブレーメンは、小さな古い町であるが、古いものと新しいものが調和した落ち着いた町との印象がある。旧市庁舎の地下のレストランには、600余種のワインが貯蔵されているとのことであるが、ローソクの灯りの下、ワインを味わいながらの夕食は、雰囲気も良くこの上ないものであった。
ブレーメンからその日の宿泊地・ベルギーのディナンへの移動は、デュッセルドルフ迄の300km余をアウトバーンをバスで、そして、飛行機でブラッセルへ。更に、目的地ディナン迄100km余は、またバスでの旅となり、強行軍の移動スケジュールであった。ブレーメンのホテルを朝6時に出発し、ディナンに着いたのは夕方であった。
僅かな自由時間の中で、ディナンの町を見学した。一方が岩山に囲われ、ミューズ川沿いに位置した小さな静かな町であった。岩山の上には城砦が築かれ、川沿いに建てられた古い教会とのコントラストは、旅人の心を捕らえるのに余りあるものがあった。教会の中の見事と言う他に言い様のないステンドグラスの輝きは今尚、脳裏に残っている。
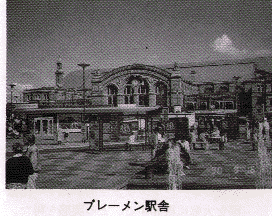 翌日、ベルギー、フランス国境をバスで越えたが、92年のEC統合を前にして、日本人がイメージしている様な国境はなかった。
翌日、ベルギー、フランス国境をバスで越えたが、92年のEC統合を前にして、日本人がイメージしている様な国境はなかった。
見渡すかぎり広大な草原(牧草地か?)を、バスはパリを目指して走った。その広大さに日本とフランスの潜在的な国力の差を見た様な気がした。4時間余り走ってエッフェル塔が見えたのは、夕暮れも近い頃であった。全員で懇親会を兼ねたパリでの夕食は、日本の会席料理にも似たフランス料理を食べながら、残り少ない旅を惜しみ、またこれまでの旅の想い出を語り合うには、この上ない場となり、盛り上がるものとなった。
参加者全員の協力と、良き添乗員に恵まれ、事故もなく、楽しく有意義な15日間にわたる調査旅行を終えることができたことに感謝したいと思う。
尚、本調査団の報告書は、近々完成する予定である。

■JR総合指令室、川崎地下街“アゼリア”防災センター及び国立国会図書館新館見学記■
通産省工技院の大型プロジェクト「大深度地下空間開発技術の研究開発」の研究会活動の一環として、去る10月15日にJRの東海道・山陽新幹線総合指令室並びに川崎地下街“アゼリア”の防災センター及び10月23日に国立国会図書館新館の見学を実施した。
新幹線総合指令室では、東京〜博多間1,000kmを走る500本/日以上もの列車を統制し安全のための統括管理を行っている。ここでは、新幹線運転管理システム(コムトラック)と新幹線情報管理システム(スミス)の他、3種類の制御装置を駆使し、JR東海、JR西日本合わせて総員約50名の指令員が、輸送、運用、施設、電力並びに信号通信の5つの指令業務を昼夜を問わず行っている。指令室には各指令業務別に整然と配置されたデスク上にCRTとプリンターが所狭しと並べられており、CRT画面上にオンラインにて表示される様々な管理データに基づいて、安全、確実且つスピーディな指令が可能となっている。安全性と信頼性を世界に誇る新幹線の技術力の高さの一端をかい間見ることができた。
川崎地下街“アゼリア”は、5省庁通達後に建設された地下街として注目されている。このアゼリアの防災を司る防災センターは、川崎駅から中央広場につながる階段下に位置し、様々な最新鋭防災設備の中枢を担っている。アゼリアの防災に対する万全の姿勢は、設備面だけではなく、単純明快な動線計画、広い公共歩道(店舗面積の1.12倍)にも現れており、すべての地点から総避難時間210秒以下を達成している。また、地下の暗い雰囲気を一掃するため、自然光の採光、白を基調とした内装或は全歩道500Lxの照明等、快適な環境創出のための心遣いも伺えた。
今後、大深度地下空間の環境防災を考えていく上で、これらの施設における基本思想を参考にし、更に安全且つ快適な空間構築を目指す意を強くした。
国立国会図書館は昭和61年度に一部を除いて完成したものである。
新館を建設するに当たっては、特に周囲との景観上のバランスから4階より高くできない事と、地下に非常に良好な地盤(東京礫層)が得られることから、東西約148m南北約43m、地上4階地下8階の細長くて下に深く延びた建物となった。現段階では、地下7、8階は未完成であるが、完成の暁には750万冊の資料が収蔵でき、本館(収蔵能力450万冊)と合わせると1,200万冊の収蔵能力となる。
地下書庫は盗難防止のため出納作業員(常時22名)以外は通常立入禁止となっている(一階にある階段入口、エレベータホールは電子ロックキーで施錠され、非常時以外は鍵にて開閉)。また、地下は書庫(出版物の永久保存)が主目的であり、空調により温度22℃、湿度55%に常に保つとともに、地下にはトイレも無く、水気をシャットアウトしている。
エレベータで地階に降りると、プーンと古本屋の臭いが鼻に付く。廊下の壁は東側緑、西側ピンクと色別され、方角がすぐ分るようになっており、書架の間をまわっても迷わないようになっている。
建物の西側の中央にはアトリウムがあり、地下の最下層迄光の届く光庭が設けられ、地下の書庫に一日居る人にはホッとした安らぎを与えている。
消化設備としては、初期消火用として粉末消火器を各階に3箇所づつ設置、完全消火用にハロゲンガス消火装置を防火区画毎(各階東と西に二分割)に2系統設置し、水による消火は考えていない。
以上のように、地下の利用形態が書庫と非常に特異性のものではあるが、アトリウムを設けて完全な密閉空間とせずに、書庫のイメージアップを図っている。

■会員の皆様へのお知らせ■
●サロン・ド・エナ(第119回)のお知らせ
| 1.日 時 |
平成2年11月28日(水)17:30〜20:00
(今回はシンポジウム’90開催のため第4水曜日となります) |
| 2.場 所 |
当協会 A・B会議室 |
| 3.テーマ |
「90年代の通産政策ビジョン」−地球時代の人間的価値の創造へ− |
| 講 師 |
大宮 正殿 通商産業省 大臣官房企画室長 |
| 4.会 費 |
3,000円(非会員5,000円) |
| 5.申込み |
地下センター 中村まで
TEL:502−3671 FAX:502−3265 |
●サロン・ド・エナ(第120回)のお知らせ
| 1.日 時 |
平成2年12月19日(水)17:30〜20:00 |
| 2.場 所 |
当協会 A・B会議室 |
| 3.テーマ |
「ドーバー海峡トンネル工事施工について」(仮称) |
| 講 師 |
宇賀 克夫殿 川崎重工業㈱ 産機プラント事業部土木機械部長
広川 宏殿 三菱重工業㈱ 神戸造船所建設機械部長 |
| 4.会 費 |
3,000円(非会員5,000円) |
| 5.申込み |
地下センター 中村まで
TEL:502−3671 FAX:502−3265 |

|